 |
|
|
|
|
|
|
|
市民に親しまれるトンボ池を目指して |
|
|
|
|
|
|
|
萩の台公園が整備され2年〜3年が経過して、くぼ地の水溜まり(トンボ池)にはヨシ・ガマが群生し、イ・トクサ・カヤツリグサが定着しています。
池のまわりにはニワゼキショウ・シロツメクサ・カラスノエンドウなどが彩りをそえ、水面にはいろいろなトンボが飛来し、水の中には各種の水生生物も生息しています。
自然のままにまかせた池を整備し、水の流れをつくりだすことで多様な生物が生息できる環境をつくりだすことができると思われます。
|
|
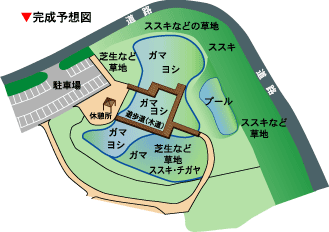 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ビオトープづくりの予定(1年目) |
|
|
|
|
|
|
|
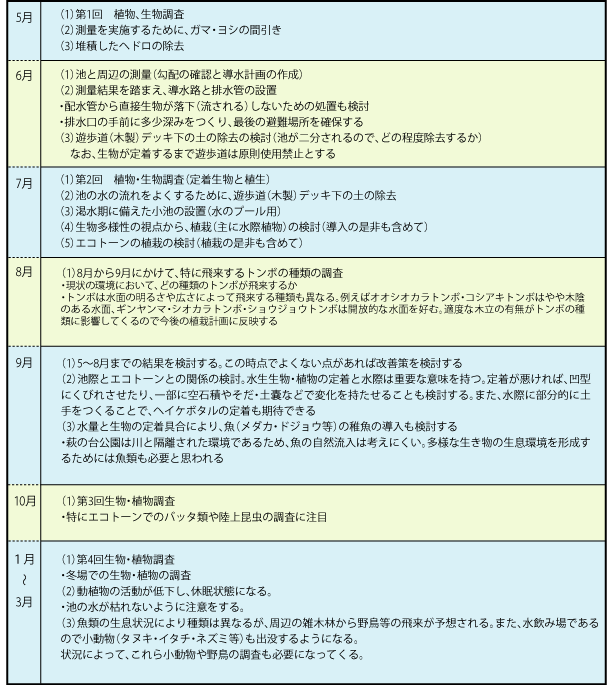 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※1年間の試行期間の結果をふまえ、2年目以降の計画を検討する。
※2ビオトープに対する考え方で、今後の管理運営方法は大きく変わる。自然に極力手を加えないのか、新たに自然を創り出すのか。1年間の試行後に根本的な議論を行う必要がある。
●現在想定される検討ポイント
(1)全国的にトンボやカエルの種類が減少している。理由として、トンボは田んぼに産卵するため冬も水をはった水田が必要であるが、現在は乾田が主であるため条件が悪い。また、稲の早生品種が増えたため、トンボの生態サイクルと合わなくなっていることも考えられる。萩の台トンボ池では、常に水を絶やさず(水質は落ちても水位は5〜15cmもあればよい)、水生植物の維持につとめてトンボのすめる環境づくりを心がける。
(2)生物多様性の観点からメダカなどの導入、水辺にヤナギなどの樹木(数本程度)、ヒツジグサやヒシなどの導入と適正管理なども考えられる。
(3)変化のある水際をつくりだし、多様な生物が定着しやすくする方法も考えられる。
(4)景観的に、エコトーンの外縁部に花木類の植栽も検討できる。
(5)チョウや野鳥の好む樹木や草花の導入も検討できる。 |
|
|
|
|
|
|